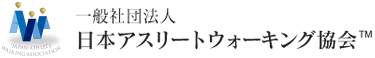「自社の福利厚生、従業員に活用されている実感はありますか?」
給与以外の報酬制度である福利厚生は、従業員満足度の向上だけでなく、企業の持続可能な成長に不可欠な戦略要素です。
本記事では、法定・法定外の福利厚生制度の違いから、導入のコツ、注目のプログラム事例までを網羅的にご紹介。福利厚生制度の整備を“コスト”ではなく“投資”と捉え、従業員に選ばれる組織づくりの第一歩をお手伝いします。
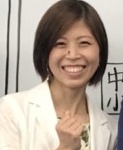 【記事担当】
【記事担当】一般社団法人日本アスリートウォーキング協会 健康経営エキスパートアドバイザー 竹内尚子
社会福祉士・精神保健福祉士
社会福祉士・精神保健福祉士として福祉行政に10年従事。その後、健康経営エキスパートアドバイザー資格を取得し、働く人々の健康サポートに取り組む。現在は企業への健康経営導入支援や、ウォーキング研修を中心としたヘルスケアプログラムの提供を通じて、従業員の健康促進に尽力中。
■目次
- 福利厚生とは?
- 福利厚生の種類
- 福利厚生の導入で得られる4つの効果
- 福利厚生導入時に気をつけたい3つの課題
- 福利厚生の導入ポイント
- 企業が注目すべき福利厚生プログラム5選
- まとめ
1.福利厚生とは?
福利厚生とは、企業が従業員に提供する給与以外の報酬や支援制度を指し、職場環境の質向上や働きがいの創出を目的としています。従業員の満足度と生産性を高めながら、企業の持続可能な成長を支える重要な仕組みです。
近年は、福利厚生が単なる“生活支援”の枠を超え、健康経営や人材戦略の一環として位置づけられるようになっています。なお、健康経営との違いや連携のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。▶健康経営と福利厚生の違いとは?
◆福利厚生の目的
- 働きやすい環境づくりを支援することで、従業員の生活の質を向上
- 従業員のモチベーションやパフォーマンスを高め、定着率の向上に寄与
- 企業ブランドの信頼性や魅力を強化し、優秀な人材の確保を促進
◆福利厚生の対象者
- 原則すべての従業員が対象
- 制度によっては、正社員のみ・勤続年数等の条件付きケースもあり
- 公平性と柔軟性を両立した制度設計が重要
◆福利厚生の予算と費用
- 制度導入にはコスト管理が不可欠
- 社員ニーズをもとに優先順位を設定し、費用対効果を最大化
- 外部サービスの活用による効率的な運用も視野に
2.福利厚生の種類
福利厚生は大きく「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」に分けられます。それぞれに役割や提供義務が異なり、企業の制度設計においてはこの分類を踏まえた戦略的運用が求められます。
◆⚖法定福利厚生(義務的に提供すべき制度)
法律で定められた最低限の社会保障制度であり、企業は全従業員に対して提供する義務があります。従業員が安心して働ける環境づくりの基盤となる制度です。
健康保険
従業員が病気やけがをした際に、医療費の一部を公的保険で補償する制度です。保険料は企業と従業員がそれぞれ負担し、家族も被保険者として医療費の支援を受けられます。
厚生年金保険
老後の生活資金や障害・死亡時の遺族年金を支給する制度で、国民年金とあわせて給付されます。企業は加入義務があり、保険料を従業員と折半で納めます。
労災保険(労働者災害補償保険)
業務中の事故や通勤途上のけがに対し、治療費や休業補償を提供する制度です。全額を企業が負担し、従業員の安全と安心を支える役割を担っています。
雇用保険
失業した際の給付や育児・介護休業中の給付金、職業訓練の支援などを含む制度です。企業は対象従業員に対して加入義務があり、キャリアの安定と再就職支援を促します。
◆🏢法定外福利厚生(企業が任意で提供する制度)
企業が自主的に提供する制度で、食事補助やスポーツクラブ利用支援など多岐にわたります。企業の独自性が反映されやすく、従業員への価値提供や職場の魅力向上に寄与します。
健康診断・人間ドックの補助
従業員の健康維持に貢献する制度です。企業が費用の一部を補助することで、病気の早期発見につながります。
【導入例】IT企業A社では、全社員に年1回の人間ドック補助を提供し、健康診断受診率95%を達成。
食事補助・社員食堂
社員食堂の設置や、食事チケットの配布により従業員の食生活をサポートします。健康志向のメニュー提供によって、健康づくりの環境が整います。
通勤手当・交通費支援
通勤にかかる交通費の支給や定期代補助によって、従業員の負担を軽減し、働きやすさを確保します。リモートワークとの併用で柔軟な設計も可能です。
育児・介護支援制度
企業内託児所や育児休業の取得促進、介護支援休暇など、家庭と仕事を両立するための支援策を整備します。働く世代の安心感と定着率向上に寄与します。
住宅手当・社宅制度
従業員の住環境の支援を目的に、住宅手当の支給や社宅の提供を行う制度です。地域やライフステージに応じた柔軟な対応が可能です。
レクリエーション支援
社員旅行やクラブ活動費の補助など、社内交流やリフレッシュを促進する制度です。職場の人間関係の活性化やモチベーション向上につながります。
3.福利厚生の導入で得られる4つの効果
福利厚生は「従業員満足」のためだけではなく、企業の競争力や経営効率を高める重要な施策です。ここでは、福利厚生の導入・強化によって得られる主な効果を整理し、制度整備の具体的な意義を明らかにします。
◆🚀従業員の生産性向上
健康支援や働きやすい環境の提供は、業務効率の向上に直結します。
福利厚生が整備された職場では、集中力や勤続意欲が高まり、チーム全体のパフォーマンスも底上げされます。
◆🎯人材確保と定着率の改善
魅力的な制度設計は、求職者からの応募意欲を高めると同時に、既存従業員の定着にもつながります。
福利厚生を通じて企業文化への共感が深まり、「この会社で働き続けたい」という気持ちを育むことができます。
◆🏢企業ブランドと魅力の向上
福利厚生の充実は、従業員からの信頼獲得だけでなく、社外へのブランディングにも好影響を与えます。
採用広報やCSR活動の一環としても発信しやすく、企業の姿勢がステークホルダーに伝わります。
◆💰法人税コストの削減
福利厚生の一部費用は、税務上「損金」扱いとなるケースがあり、節税効果が期待できます。
制度設計と会計処理の工夫によって、財務負担の最適化を図ることも可能です。
💡補足コラム💡
「福利厚生は“コスト”ではなく“投資”」という視点を持つことで、経営層の理解・予算化もスムーズになります。
4.福利厚生導入時に気をつけたい3つの課題
福利厚生制度には多くのメリットがありますが、導入や運用には一定のリスクも伴います。このセクションでは、制度整備における課題とその対策について具体的に整理します。
◆🔄課題①:利用率が想定より低い
制度が整っていても、従業員の認知や利用が進まなければ成果につながりません。特にニーズに合っていない施策は「形だけの福利厚生」となってしまうことも。
対策例:
- 制度設計前にアンケート・ヒアリングで従業員の声を収集
- 導入後も説明会や社内報で制度の周知と活用事例を共有
- 利用率データを定期的に分析し、必要に応じて見直しを行う
◆💰課題②:コスト負担が増える
法定外制度や外部サービス活用では、企業側の金銭的負担が増す可能性があります。経営層が「費用対効果」に懸念を持つことも少なくありません。
対策例:
- 優先順位を明確にし、投資価値の高い施策から段階的に導入
- 福利厚生費が損金算入できる項目は税務面からも活用
- 社内リソースではなく、外部連携による効率化も検討
◆📋課題③:制度運用の管理が煩雑になる
複数の制度を抱えると、社内管理の負担が増加し、業務効率に影響を与える場合もあります。
対策例:
- 専門部署や担当者の設置、もしくは兼務体制の明確化
- クラウド型福利厚生管理ツールの導入
- 外部委託サービス(福利厚生アウトソーシング)との連携
💡補足コラム💡
福利厚生制度は「導入後の管理・評価」まで含めて設計することで、持続的な運用が可能になります。
5.福利厚生の導入ポイント
福利厚生制度の効果を最大化するには、単なる導入ではなく、従業員に届き、使われ、継続される設計・運用が欠かせません。ここでは、制度整備の成功に向けた4つの重要ポイントを紹介します。
◆🧭ニーズに合わせたプランニング
まずは従業員の本音を把握することからスタート。よくある施策を“とりあえず”導入するのではなく、「自社らしさ」や「働く人の声」に耳を傾けた設計が求められます。
導入前にやるべきこと:
- 社内アンケートやヒアリングの実施
- 社員層(年代・ライフステージ・勤務地)の分析
- 他社事例との比較で差別化ポイントを明確化
◆📣従業員への情報提供と教育
制度があっても内容が知られていなければ活用されません。従業員が制度の“意義と使い方”を理解するためのコミュニケーションが不可欠です。
おすすめ施策:
- 説明会やオンボーディング研修で制度の紹介
- 利用事例の共有やインタビューを社内報で掲載
- FAQコンテンツの整備で情報アクセスの手間を削減
◆🤝外部サービスの活用
専門性が必要な制度(健康支援・メンタルケア・社宅管理など)は、外部連携によって社内負担を減らしながら高品質な制度導入が可能に。
活用のポイント:
- 自社での運用が難しい領域は積極的にアウトソース
- 福利厚生パッケージサービスの比較検討
- 社員満足度や導入事例のある事業者を選定
◆🔄福利厚生の評価と改善
制度は「導入して終わり」ではなく、定期的な見直しと改善が重要です。運用状況を可視化しながら、従業員の声を反映して柔軟な制度進化を図りましょう。
改善プロセス例:
- 利用率・満足度の定期調査
- 管理部門や従業員代表による制度評価ミーティング
- 新しい働き方(例:ハイブリッド勤務)への適応
6.企業が注目すべき福利厚生プログラム5選
自社に最適な福利厚生制度は、従業員の属性や組織文化、働き方に応じて異なります。ここでは近年注目されている5つの制度をピックアップし、それぞれの特徴と導入効果を紹介します。
◆💻リモートワーク支援制度
在宅勤務の普及に伴い、従業員の作業環境整備を支援する制度が増えています。
導入例:
- 通信費や在宅設備購入の補助
- デジタルコミュニケーション研修の実施
→ 働きやすさと生産性の両立を実現
◆👶企業内託児所の設置
育児中の従業員が安心して働ける環境を整えることで、離職防止と人材活用につながります。
導入メリット:
- 子育て世代の定着率向上
- 多様な人材の活躍推進
→ ダイバーシティ経営の一手として有効
◆🧠メンタルヘルスケアプログラム
心の健康管理は従業員満足だけでなく、業務パフォーマンスにも直結する重要テーマです。
施策例:
- 専門カウンセラーによる相談窓口設置
- ストレスマネジメント研修の定期実施
→ 長期的な人材活用・安定経営への寄与
◆🏃♂️ヘルスケアプログラム(当社提供)
ウォーキングを中心に、ウェアラブルデバイスや個別アドバイスを活用して楽しみながら健康維持を促進しています。
特徴:
- 自主性と継続性を高める参加型設計
- チームビルディング効果も兼備
→ 健康経営とエンゲージメント向上の両立を支援
◆⏰フレックスタイム制度
従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を可能にする制度です。
導入効果:
- 通勤ストレスの軽減
- 自主性の尊重による満足度アップ
→ ワークライフバランスの実現に直結
7.まとめ
福利厚生は、単なる“従業員満足のための制度”ではなく、企業の持続的成長や人材戦略を支える重要な経営投資です。法定・法定外の制度を正しく理解し、自社の文化や従業員ニーズに合ったプログラムを設計することで、職場の魅力と生産性を高めることができます。
特にこれからの企業経営では、「選ばれる職場」「信頼される組織」を目指すうえで、福利厚生の在り方そのものが競争力のひとつになります。
まずは、既存制度が従業員に届いているかを見直し、改善の余地を明確にすることから始めてみましょう。当社ではヘルスケア領域での支援プログラムをはじめ、貴社の制度設計をサポートするコンサルティングもご提供しています。ご興味があればお気軽にお問い合わせください。
▶【関連記事】健康経営と福利厚生の違いをさらに深く理解したい方はこちら
🏃♂️ ヘルスケアプログラム(ウォーキング講座・研修)の開催について
個人・法人向けのウォーキング講座や研修を開催しています。
• 個人の方:こちらから開催状況をご確認ください。
• 法人の方:お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。