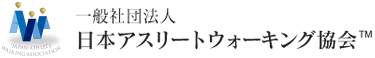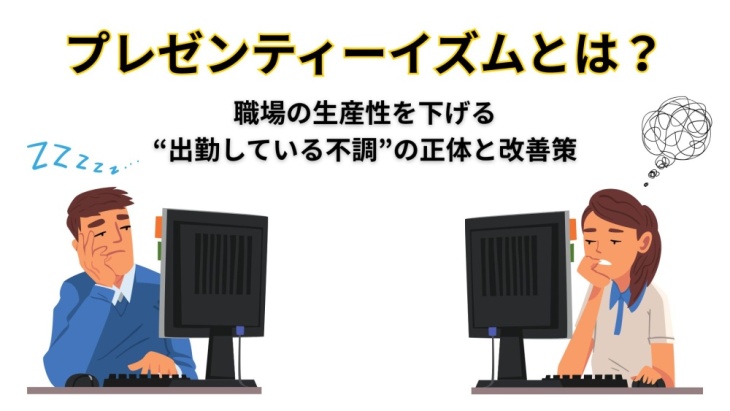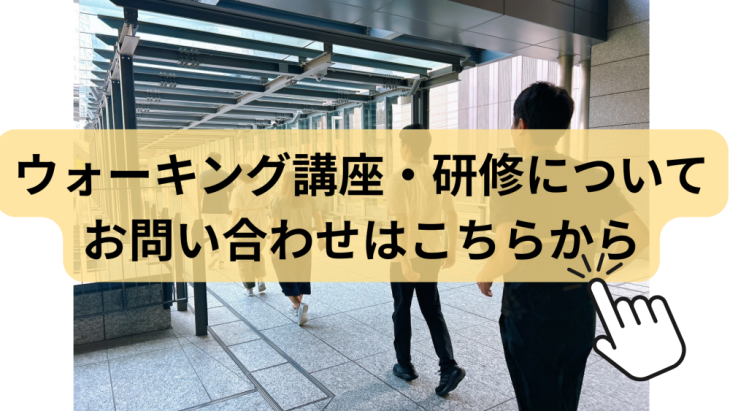最近、職場で “なんとなく不調だけど休めない” という声を耳にしませんか?
それはもしかすると『プレゼンティーイズム』かもしれません。出勤しているけれど、心身の不調により本来のパフォーマンスが発揮できない状態――それがプレゼンティーイズムです。
一方で、欠勤による損失を指す『アブセンティーイズム』と混同されがちですが、両者は職場の生産性や健康経営において、異なる課題を抱えています。
本記事では、プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムの違いをわかりやすく解説しながら、企業や組織が取り組むべき改善策や予防法についてご紹介します。従業員の健康と働きやすさを守るために、今こそ知っておきたい内容です。
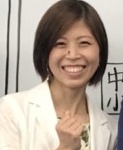 【記事担当】
【記事担当】一般社団法人日本アスリートウォーキング協会 健康経営エキスパートアドバイザー 竹内尚子
社会福祉士・精神保健福祉士
社会福祉士・精神保健福祉士として福祉行政に10年従事。その後、健康経営エキスパートアドバイザー資格を取得し、働く人々の健康サポートに取り組む。現在は企業への健康経営導入支援や、ウォーキング研修を中心としたヘルスケアプログラムの提供を通じて、従業員の健康促進に尽力中。
■目次
- プレゼンティーイズムとは?“出勤している不調”の意味と背景
- アブセンティーイズムとは?欠勤による損失との違い
- 職場に潜むリスク:プレゼンティーイズムがもたらす影響とは
- プレゼンティーイズムの実態をどう把握する?測定方法を解説
- 今すぐできる!プレゼンティーイズムの予防と改善アプローチ
- まとめ:健康経営の第一歩は”気づくこと”から
🟦 プレゼンティーイズムとは?“出勤している不調”の意味と背景
「プレゼンティーイズム(Presenteeism)」とは、従業員が体調不良や精神的な不調を抱えながらも出勤し、通常のパフォーマンスを発揮できない状態を指します。表面的には“出勤している”ため、欠勤のように目に見える問題ではありませんが、実は企業の生産性や業績に大きな影響を与える隠れたリスクです。
🔍 なぜ問題なのか?
- パフォーマンスの低下:集中力や判断力が鈍り、業務効率が落ちる
- ミスや事故の増加:注意力の低下により、ヒューマンエラーが起こりやすくなる
- 周囲への影響:不調を抱えたまま働くことで、職場の雰囲気やチームワークにも悪影響を及ぼす可能性がある
- 長期的な健康悪化:無理な出勤が慢性化すると、症状が悪化し、結果的に長期離脱につながることも
🧠 背景にある心理
プレゼンティーイズムは、単なる「根性論」や「責任感」だけで起こるものではありません。
「休むと迷惑をかける」「評価が下がるかもしれない」「仕事が溜まるのが怖い」といった心理的なプレッシャーや、職場文化・制度の影響が大きく関係しています。
🟦 アブセンティーイズムとは?欠勤による損失との違い
「アブセンティーイズム(Absenteeism)」とは、従業員が病気や私的な理由などで職場を欠勤することを指します。こちらはプレゼンティーイズムとは異なり、“物理的に職場に不在”であるため、企業側も把握しやすく、管理や対応がしやすい傾向があります。
🔍 欠勤がもたらす影響
- 業務の停滞:担当者が不在になることで、業務の進行が遅れる
- 他の従業員への負担増:欠勤者の業務をカバーするため、周囲の負荷が高まる
- チームの生産性低下:連携やコミュニケーションが滞り、チーム全体の効率が落ちる
- 人件費のロス:有給休暇や病欠によるコストが積み重なる
🧠 背景にある要因
アブセンティーイズムの原因は多岐にわたります。
身体的な病気やメンタルヘルスの不調だけでなく、職場環境や人間関係、家庭の事情なども影響します。特に、職場のストレスやハラスメントが原因で欠勤が増えるケースもあり、企業としては早期の対応が求められます。
このように、プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムは「出勤しているかどうか」という違いはありますが、どちらも職場の生産性や従業員の健康に深く関わる重要な課題です。
🟦 職場に潜むリスク:プレゼンティーイズムがもたらす影響とは
プレゼンティーイズムは、見た目には「出勤している」ため一見問題がないように見えますが、実際には職場の生産性や経済的損失に大きな影響を及ぼします。企業が見過ごしがちなこの課題に、いかに早く気づき、対策を講じるかが重要です。
🔧 生産性への影響
- 業務効率の低下:体調不良や精神的な不調により、集中力や判断力が鈍り、業務の質が下がります
- チーム全体への波及:不調者がいることで、周囲のメンバーがフォローに回り、チーム全体の生産性が落ちる可能性があります
- 創造性や提案力の低下:本来の力を発揮できないことで、アイデアや改善提案が出にくくなる
💸 損失額への影響
プレゼンティーイズムによる損失は、アブセンティーイズム以上に深刻とされることもあります。
例えば、ある調査では従業員の健康不調による生産性損失額が、欠勤による損失の数倍に及ぶという結果も報告されています。
- 見えないコスト:業務の遅延、品質低下、顧客対応の不備などが積み重なり、企業の信頼や収益に影響
- 長期的な医療費の増加:不調を抱えたまま働き続けることで、症状が悪化し、医療費や休職リスクが高まる
🟦 プレゼンティーイズムの実態をどう把握する?測定方法を解説
プレゼンティーイズムは目に見えにくいため、企業がその実態を把握するには、定期的かつ多角的なアプローチが必要です。ここでは、代表的な測定方法をご紹介します。
🧪 ストレスチェックテストの実施
労働安全衛生法に基づき、従業員の心理的ストレスを把握するために行われる「ストレスチェック」は、プレゼンティーイズムの兆候を早期に発見する有効な手段です。
- 高ストレス者の傾向を把握
- 部署ごとの傾向分析により、職場環境の改善にもつながる
- 定期的な実施で、変化を追跡できる
📊 従業員サーベイの実施
業務満足度や健康状態、職場環境に関するアンケートを定期的に実施することで、プレゼンティーイズムのリスクを可視化できます。
- 「最近、業務に集中できていますか?」などの質問で兆候を探る
- 匿名性を確保することで、率直な回答が得られやすい
- 組織全体の傾向を把握し、改善施策の根拠にできる
🗣 1on1など管理職からのヒアリングの実施
直属の上司による1on1ミーティングは、従業員のコンディションを把握するうえで非常に有効です。
- 表情や話し方から、言葉にできない不調を察知できる
- 業務だけでなく、プライベートの状況も含めた対話が信頼関係を築く
- 定期的な実施で、早期のフォローや支援が可能に
このように、プレゼンティーイズムの測定には「数値」と「対話」の両面からのアプローチが重要です。
🟦 今すぐできる!プレゼンティーイズムの予防と改善アプローチ
プレゼンティーイズムを未然に防ぎ、従業員が本来の力を発揮できる職場環境を整えるためには、多層的なケアの仕組みが必要です。ここでは、セルフケアから専門家による支援まで、具体的な対策をご紹介します。
🧘 セルフケア
従業員自身が心身の状態に気づき、適切に対処する力を育むことが基本です。
- 健康診断やストレスチェックの結果を活用し、自分の傾向を把握
- 睡眠・食事・運動など生活習慣の見直し
- メンタルヘルスに関する情報提供やセルフチェックツールの活用
🚶♀️ ウォーキング研修によるセルフケア支援
プレゼンティーイズムの予防には、従業員自身が心身の状態を整える「セルフケア」の習慣化が欠かせません。その一環として、弊社では、プレゼンティーイズムの予防と従業員のセルフケア意識向上を目的に、「ウォーキング研修」を導入しています。これは、ただ歩くだけではなく、姿勢・呼吸・歩き方のコツを学びながら、心身のバランスを整える実践的なプログラムです。
ウォーキングには、血流促進やストレス軽減、集中力の向上など、心身にポジティブな影響をもたらす効果が期待されます。研修では、日常に取り入れやすい運動習慣として、従業員が無理なく継続できるよう工夫しています。
- 身体的なリズムの回復:軽い運動により血流が促進され、疲労感や倦怠感の軽減につながる
- メンタルケア効果:自然の中を歩くことで気分転換になり、ストレスの緩和にも効果的
- コミュニケーションの促進:参加者同士の交流が生まれ、孤立感の防止や職場の雰囲気改善にも貢献
実際の参加者からは、「気持ちが前向きになった」「仕事に集中できるようになった」といった声が多く寄せられており、プレゼンティーイズムの予防だけでなく、職場の活性化にもつながっています。
今後も弊社では、従業員の健康と働きやすさを支える取り組みとして、ウォーキング研修をはじめとしたセルフケア支援を継続的に推進してまいります。
🤝 ラインケア(管理職による支援)
直属の上司が部下の不調に気づき、早期に対応することが重要です。
- 定期的な1on1ミーティングの実施
- 業務量や働き方の調整
- 不調を訴えやすい職場の雰囲気づくり
- 管理職向けのメンタルヘルス研修の導入
🩺 産業保健スタッフのケア
産業医や保健師などの専門職による支援は、より専門的な対応が可能です。
- 高ストレス者への個別面談
- 職場環境の改善提案
- 従業員への健康教育や相談窓口の設置
🌐 職場外の専門家のケア
社外のカウンセラーやEAP(従業員支援プログラム)などを活用することで、社内では対応しきれない課題にも対応できます。
- 匿名で相談できる外部窓口の設置
- 家庭やプライベートの悩みにも対応可能
- 専門的な心理療法や医療機関との連携
このように、プレゼンティーイズムへの対処は「個人」「職場」「専門家」の三位一体で取り組むことが理想です。
🟦 まとめ:健康経営の第一歩は“気づくこと”から
プレゼンティーイズムは、出勤しているにもかかわらず心身の不調によって本来の力を発揮できない状態であり、企業にとっては“見えにくい損失”を生む深刻な課題です。一方、アブセンティーイズムは欠勤による損失であり、両者は異なる性質を持ちながらも、職場の生産性や従業員の健康に大きく関わっています。
この記事では、プレゼンティーイズムの定義から職場への影響、測定方法、そして予防・対処法までを網羅的にご紹介しました。重要なのは、個人・職場・専門家が連携し、早期に気づき、支援する体制を整えることです。
健康経営の推進や働き方改革が求められる今、プレゼンティーイズムへの理解と対策は、企業の持続的な成長に欠かせない要素となっています。
従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりのために、ぜひ今日からできることから始めてみましょう。